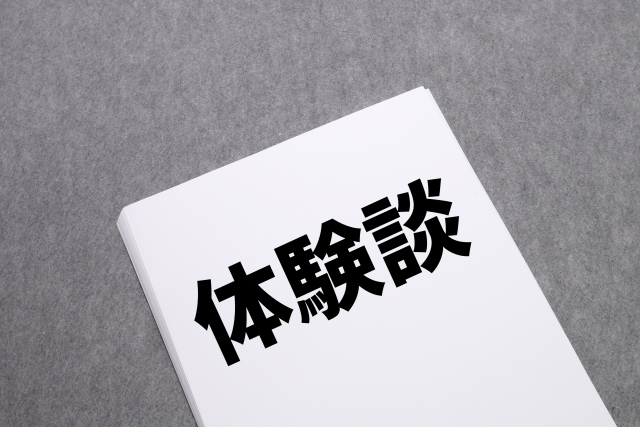年末年始は外で食事をする機会が多く、楽しかったのですが少し忙しかったです。
正月休み、一緒に飲みに行った友達から「ノンアルコール飲んだのに、飲酒運転だって警察に捕まった人がいるんだけど、どうなっているんだろう?」と聞かれました。
ノンアルコール飲料は、飲み会で飲めない時にもそれっぽいものを味わえる便利なアイテムなのですが、注意が必要です。
今回はこんなお話です。
ノンアルコール飲料を飲んだのになぜ?
よく聞く「飲酒運転」は、正式には「酒気帯び運転」と言われています。
一般的なノンアルコールのビールは、よほど量を飲まなければ検出されず、気帯びにはなりません。
ノンアルコールのドリンクは、わずかにアルコールが入っている場合があり、短時間で大量に飲んだ場合は、ごくたまにアルコールが検出されてしまい、「酒気帯び」になる可能性があります。
最初に友人から聞いた話は、このパターンかもしれません。
表記「0.00%」でもわずかにアルコールが入っている場合
現在、いくつかのビール会社がノンアルコールビールを販売しており、アルコールの入ったビールと、ほぼ同じ味の高いクオリティが人気です。
もちろん「アルコール0.00%」と表記があるものの、0.00%と書かれていても全くアルコールが入っているわけではありません。
アルコールが0.005%未満の場合でも0.00%と表記でいるため、ごこわずかですが、アルコールが入っている可能性があるのです。
とはいっても、あまり心配しなくてよいと思います。
短時間で大量に飲酒しなければ、アルコールは検出されないでしょう。
ノンアルコールビールを飲んだ後に運転をする際は、ノンアルコールのドリンクはゆっくり少しずつ飲むことを心掛けてください。
ノンアルコールビール以外の選択肢はあるの?
さてノンアルコールの飲料というと、一番に思い浮かべるのがノンアルコールのビールだと思います。
しかし、アルコールが全く入っていないわけではない、ということを知ると少し怖くなるかもしれませんね。
お茶や水ならよいかもしれませんが、ほかの人がアルコールを飲んでいるのを見ると、つまらないくなるかもしれません。
個人的に試したのですが、家で飲み会をする場合には、甘くない強炭酸水にレモンを入れると、レモンサワーのような味になります。
居酒屋さんではレモンサワーではなくレモン水を扱っているお店もあるので、ノンアルコ―ル飲料の代わりに注文するのもよいと思います。